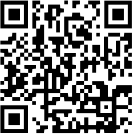三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科を運営する医療法人D.D.Orthoが監修しています。
医療費控除と矯正
こんにちは、三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科の院長 内澤です。
1月も中旬となり、確定申告の時期も近づいてきましたね。
そこで、本日は医療控除についてまとめます。
医療費控除とは
所得控除のひとつです。
医療費(1月1日から12月31日までの一年の間)の額を基に計算され、医療費が一定額以上超えると所得控除を受けることができます。
医療費は、生計を同じにする家族全員分の医療費を合計した金額となります。
医療費控除の対象となる医療費
1.生計を同じにする家族全員分の医療費
2.1月1日から12月31日までの1年の間の医療費
医療控除の計算方法
医療控除は以下の式で計算されます。
(一年間に実際に支払った医療費)-(保険金等で補充される金額)-(10万円もしくは総所得の5%を比較した低い金額)
注)医療費控除の最高額は200万円です。
医療費控除の対象
基本的に、医療費控除が認められるのは、歯並びを美しく整えたいという審美目的ではなく、機能障害として診断名がつく場合や、子供の矯正など社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用が、医療費控除の対象になります。このため、美容目的の矯正治療の場合は医療控除の対象になりません。
通院のための交通費も医療控除の対象になります。本人の、通院に必要な交通費はもちろんのこと、医療を受ける方が若年者で保護者の同伴が必要な場合には、保護者の交通費も対象となります。
申告時期
医療費還付申告は確定申告の時期以外でも申告可能です。
また5年前までさかのぼって申告できます。
注意
医療費控除は所得控除なので、納税金額(所得税納付額)が医療費控除の金額分少なくなるわけではありません。
所得税納付額の仕組み
所得税納付額の計算方法は以下の式で行われます。
(収入-必要経費-所得控除)×所得税率-税額控除=所得税納付額
収入-必要経費=所得
所得-所得控除=課税所得
課税所得×所得税率=所得税
所得税-税額控除=所得税納付額
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、扶養控除そして医療費控除などが含まれます。
所得税率と税額控除は、課税所得(収入-必要経費-所得控除で計算される金額)によって、加算される税率や控除額が変わります。
| 課税所得 | 所得税率 | 税額控除
|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円
|
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円
|
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円
|
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円
|
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円
|
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円
|
例えば
年収400万円の場合(勤務)
給料所得控除が134万円となり、また基礎控除が38万円、もしここで医療費控除以外の所得控除が7万円だったとする、
100万円の矯正治療費を1年間で支払った場合、課税所得は
400万円-134万円-38万円-7万円-90万円=131万円
課税所得が131万円なので所得税率5%、税額控除0円
つまり所得税納付額が131万円×0.05=6.55万円となります。
もし、100万円の矯正治療費の支払いがない場合、上記の計算から所得税納付額は12.35万円となります。
2年間で支払った場合(年間50万円)の所得税納付額は9.05万円となります。
4年間で支払った場合(年間25万円)の所得税納付額は10.85万円となります。
まとめ
年収、治療費総額、分割回数によって所得税納付額は変化します。