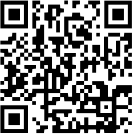三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科を運営する医療法人D.D.Orthoが監修しています。
矯正治療と虫歯歯周予防
こんにちは
現在の矯正治療は、ブラケットとワイヤーを使ったマルチブラケット法が主流です。
この矯正治療法では複雑な矯正装置を使うため、食べ物の流れが悪くなるばかりか、歯磨きもとても難しくなります。
近年、新しく登場し、目立たない、取り外しができるなどの利点から、当院でも需要が高まっているインビザラインのようなマウスピース矯正なら、歯磨きはしやすくなります。
ですが、つけている間の唾液の流れが悪くなることから、唾液の持つ汚れを洗い流す働きや虫歯菌の活動を抑える働き、初期虫歯を治す働きが発揮できなくなります。
マルチブラケット法、インビザライン、ともに矯正治療中の虫歯のリスクからは逃れられないようです。
そのため、矯正治療中は、より一層のお口のケアが望まれます。
今回は、矯正治療とお口のケアについてお話ししたいと思います。
■矯正治療での抜歯の目的
矯正治療を受けている間は、歯磨きをはじめとするお口のケアが難しくなります。
食べたものも残りやすいですし、お口の中も不潔になりやすいです。
ちょっと油断するとたちまち矯正装置の周囲に虫歯が生じたり、歯ぐきが腫れたりします。
矯正治療中は特にお口のケアが重要とされるのはこのためです。
○虫歯のリスク
虫歯の原因は、歯の表面をおおうプラークに潜んでいるストレプトコッカス・ミュータンスなどのレンサ球菌であることが明らかになっています。
プラークの中で虫歯の原因菌が、磨き残しの中の炭水化物を分解して乳酸を作り出し、この乳酸が長期にわたって歯のエナメル質に接触し続けることで、エナメル質が脱灰され虫歯が発生します。
すなわち、虫歯が発生するには、『歯』と『細菌』、『細菌のエサ』の3つの条件が揃う必要があり、どれか一つでも欠けると虫歯にはなりません。
余談ですが、わたしたち歯科医師は、学生の頃からこの3つの発生要因を円にして、それらが重なり合った図を、これでもかというほど教え込まれます。
矯正治療を受けている間は、これらの3要素が簡単に揃いやすく、虫歯になりやすい傾向が指摘されています。
○歯周病のリスク
歯周病も、細菌が原因で起こる炎症性の病気です。
歯周病の原因菌も、虫歯と同じくプラークの中にいます。
実は、プラークの場所によって細菌の種類に違いがあることがわかっています。
特に影響しやすいのが、歯と歯ぐきの隙間である歯周ポケットの中にいる嫌気性のグラム陰性桿菌です。
矯正装置が装着されると、歯周ポケットの部分にまで歯ブラシの毛先が届きにくくなりますから、歯周病のリスクも高まるのです。
■矯正治療と虫歯
矯正治療を受ける前の段階では、虫歯の原因菌が潜んでいるプラークは、歯の付け根付近、歯と歯の間、噛み合わせ面の溝、乱杭歯の重なり合っているところなどに発生しやすい傾向があります。
その他、生え切っていない歯や、上顎と下顎の前歯の裏側にもつきやすいです。
言い方を変えると、ちゃんと生えている歯の表面にはあまりついていないとも言えます。
ところが、矯正治療がいざ始まると、このプラークの付きやすいところが変化します。
矯正装置が装着されるため、お口の中の状態が複雑化するからです。
そのため、歯に部分的にプラークがつくのではなく、矯正装置の周囲を含めて、歯の表面全体にプラークがつきやすくなります。
特に注意が必要なのが、マルチブラケット法による矯正治療のときで、ひどい場合はブラケットやバンドの表面にまでプラークが付着します。
ワイヤーの下の部分も要注意です。
また、金属バンドのフィットが悪い場合は、プラークがより付着しやすくなり、セメントが溶け出し、隙間を作ってしまいます。
金属バンドと歯との隙間には歯ブラシは入らないので、この部分にプラークが溜まるとそこから虫歯が発生することになります。
一見すると歯は綺麗に磨いてあり、プラークがついていないように見えることもありますが、見えにくいだけという場合がほとんどです。
実際、プラークの染め出し液を塗ってみると、プラークの付き具合がよくわかります。
■矯正治療と歯周病
○歯列不正と歯周病
歯並びの悪い方の多くは、すでに歯周病になっている傾向がみられます。
その理由は、いろいろあります。
例えば、噛み合わせている歯や隣の歯との位置関係が良くないために、正しい噛み合わせが得られていないこと、お口が本来持っている唾液などを利用した歯の表面の汚れを洗い流す働きが下がっていることなどです。
また、歯並びが重なり合っているなどの原因で、歯ブラシが歯ぐきを適度に刺激できないことも影響していると考えられています。
多くの場合は、矯正治療を受けて歯並びが整えられると、これらの歯周病を引き起こしていると考えられる原因は解消されるため、歯周病の症状は改善されます。
しかし、これはあくまでも矯正治療が終わった後の話です。
矯正治療を受けている間は、矯正装置が入っていることでお口の中の清掃状態が悪くなってしまいます。
マルチブラケット法の矯正装置はもちろんですが、インビザラインのようなマウスピース矯正もしかりです。
プラークが増えたり、食べカスが残ったままになったりすることが、歯ぐきの腫れを引き起こすことは明らかです。
○実は子どものときから始まっている歯周病
歯周病というと、大人の病気と思われがちですが、実は小学校に入る前のお子さんの2割ほどに歯ぐきの腫れ、つまり歯肉炎が見られます。
歯肉炎も立派な歯周病のひとつです。
ここから年齢が上がり、乳歯と永久歯が混ざり合った混合歯列期という状態の年齢では、特に10代前半にかぎってみると、80%近くに歯肉炎が起こっているとも言われています。
混合歯列期が終わり、永久歯だけの歯並びになってくると、歯肉炎から歯周炎に発展します。
簡単にいうと、歯肉炎は単に歯ぐきが腫れただけの状態ですが、歯周炎は歯ぐきの腫れだけでなく、歯を支えている骨が減ってしまう歯周病です。
10代後半から20代前半でみるとおよそ70%に歯周炎が起こっています。
ちょうどこの年齢層は、矯正治療を受けている年齢層にほぼ一致します。
冒頭に、『歯並びの悪い方は矯正治療を受ける前からすでに歯周病になっている』と書いたのには、こういう背景があったわけです。
■矯正治療中の虫歯の予防
虫歯の予防法の基本は、先にご紹介した『歯』と『細菌』、『細菌のエサ』の3つの条件を断ち切ることです。
ひとつでも欠けると、虫歯は起こりません。
矯正治療中に虫歯になると、矯正装置を除去して虫歯の治療に専念しなければならなくなることもありますから、そうならないように適切に予防することが大切です。
○歯を強くする
虫歯の原因菌が作り出す乳酸にエナメル質が溶かされないようにするためには、酸に対して歯を強くすることです。
その方法が、『フッ化ナトリウム』という薬です。
みなさんが『フッ素』とよんでいらっしゃる薬は、正しくは『フッ化ナトリウム』といいます。
フッ化ナトリウムを歯に作用させると、それだけで歯を酸に対して溶かされにくい強い歯にすることができます。
フッ化ナトリウムの配合されたうがい液でうがいをしたり、フッ化ナトリウムのジェルを歯に塗ったりするほか、フッ化ナトリウムの配合された歯磨き粉で歯を磨くことも効果的です。
特に、最近では1450ppmという高濃度フッ素配合歯磨き粉が販売されていますから、日常の歯磨き粉をこれに変えるだけで、虫歯予防効果が高まります。
ただし、6歳未満のお子さんには使えないのでご注意ください。
○虫歯の原因菌を減らす
虫歯菌を減らすためには、虫歯菌が潜んでいるプラークを取り除くこと、つまりプラークコントロールが1番の対策です。
お口のケア イコール プラークコントロールと言われるほどに、プラークコントロールは、お口のケアの基本です。
プラークを取り除く方法は、歯磨きで物理的にプラークを取り除くことが最も効果的です。
矯正治療中は、歯磨きがしにくくなりますから、ワンタフトブラシなど特殊は歯ブラシを使ってみるといいでしょう。
また、プラーク自体を作り出さないようにするために、近年販売されているプラークを抑える効果のあるマウスウォッシュを使ってみるのもいいですね。
○食べ物の工夫
虫歯菌の栄養源を断つことも虫歯予防のポイントです。
具体的には、虫歯菌は、砂糖をはじめとした炭水化物から栄養を得ています。
そこで、砂糖の量を減らしたり、甘いものを食べる時間や回数を減らしたりしましょう。

虫歯・歯周病予防にはプラークコントロールが重要
■矯正治療中の歯周病の予防
プラークの中にいる歯周病菌が、歯肉炎や歯周炎を引き起こすメカニズムはいろいろ考えられています。
例えば、歯周病菌が作り出す内毒素という毒素成分や、歯周病菌自体の成分が直接的に歯ぐきの炎症を引き起こすという説や、それらに対する人間側の免疫反応が歯ぐきを傷めてしまうといった説までいろいろあります。
いずれにしても、歯周病を発症させないためには、歯周病菌を増やさないようにすることが肝要です。
そのために大切なのが、プラークコントロールです。
歯周病は、歯と歯の間の歯ぐきから始まることが多いため、歯と歯を歯間ブラシやデンタルフロスで清掃するようにしましょう。
そして、定期的にスケーリングやルートプレイニングを受けて歯石を取り除きます。
虫歯の予防では、フッ化ナトリウムを使った歯の強化ができますが、歯周病では歯ぐきを強化する方法はありません。
それゆえに、歯周病対策では、プラークコントロールがより一層重要となります。
また、最近では、歯周ポケット内にミノサイクリン塩酸塩製剤(商品名ペリオクリンr)などの抗菌薬軟膏を直接注入する治療も行われています。
これは、歯周ポケット内の歯周病菌に抗菌薬を作用させ、歯周病菌そのものを直接的にコントロールさせ、歯周病を改善しようというものです。
歯周病の悪化は、矯正治療において重要な歯を支える骨に直接的に影響を及ぼすため、適切な予防管理が重要となります。