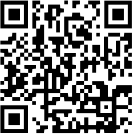三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科を運営する医療法人D.D.Orthoが監修しています。
目標と診断
こんにちは
矯正治療に限らず、医療行為には治療と目標というものがあります。
目標がなければ、治療が成功したかどうか決められませんし、何よりどのように治療を進めていくのか、どのような状態になれば治療が終了となるのかも決められなくなってしまいます。
歯科医の担当分野でいえば、虫歯治療なら『痛みをなくすこと』、歯周病の治療なら『腫れや揺れをなくすこと』といったところでしょうか。
もちろん、被せ物をセットして虫歯で失われた歯の形を回復するというのも目標でしょう。
では、矯正治療の目標は一体なんでしょうか。
『歯並びをきれいに整えること』、これはすぐに思いつくと思いますが、実はこれだけではありません。
■矯正治療での治療目標
矯正治療に先立って、いろいろな検査や診査を受けていただき、その結果を分析します。
問題となる異常箇所が、歯並びだけなのか、顎の骨も含めたものなのか、両者の関係性も含めて見出し、どの部位を治療すべきか判断します。
この診療行為を治療目標の確立とよんでいます。
治療目標となる異常としては、『歯並びや噛み合わせの異常』『上顎骨や下顎骨の骨格の異常』『横顔の異常』『お口に関係するいろいろな組織の異常』の4つが挙げられ、それぞれの改善が目標となります。
矯正治療というと歯並びをきれいに整える治療というイメージがありますが、実は、単に歯並びを良くするだけにとどまらず、お口全体の組織を良くしようというコンセプトで行われていることがわかっていただけたのではないでしょうか。
だからこそ、矯正治療は誰でもできる治療ではないのです。
普通の歯科医院でも矯正治療を手がけているところは数多くありますが、当院のように矯正歯科治療を専門に行っているところの方が、おすすめとされる背景にはこのように矯正治療の治療目標がとても複雑であるという事情があります。
■矯正歯科治療での診断はちょっと特殊
矯正歯科治療においては、『病気や病状を判断』して『病名を決定する』だけでは十分とはいえません。
矯正歯科を受診する方の病名は、『不正咬合』『歯列不正』ですが、これだけで治療方針は決定できないからです。
そのため、矯正歯科治療の診断では、単に病気や病状を判断するにとどまらず、治療方針の決定に関係する範囲まで広く判断することが求められています。
また、患者さんのお口やお顔の形に加え、『食べ物を噛む』『言葉を発する』などのお口の機能の異常について、どこまでを正常とするのか、言い方を変えると、どの程度を病気として捉えるのかも問題となります。
しかも困ったことに、現代では、矯正歯科治療に対するニーズは年々多様化の一途をたどっています。
単に歯並びをきれいに整え、噛み合わせを適切にするだけではダメで、お顔を整える、さらには横顔もきれいにしたいというご希望を叶えられるようにしなければならなくなっています。
加えて、矯正治療の方法も、目立ちにくい方法や治療期間を短くする方法が望まれるようになってきました。
当院でも人気の高いインビザラインなどのマウスピース矯正が誕生したのは、こうしたニーズがあったからです。
そのため、治療前に行う診断の持つポテンシャルは、大きくなる一方です。
このような特殊性をはらんでいるのが、矯正歯科での診断なのです。
現在では、矯正治療前のさまざまな検査や診査を経て診断をくだし、それに基づいて治療前の状態を分類して評価するようにしています。

矯正歯科治療の診断には幅広い判断が求められる
■不正咬合の分類
歯並びが整っていない状態を、不正咬合、もしくは歯列不正といいます。
いろいろな治療前の検査や診査を経て、最初に歯並びの状態を診断します。
不正咬合の分類法としては、現在、一般的にはアングルの分類という分類法が用いられています。
○アングルの分類
アングルとは、角度という意味ではありません。
この分類方法を考案したアメリカ人歯科医師の名前エドワード・アングル博士に由来しています。
アングル博士は、今では近代的な矯正治療の父とも言われているほど矯正歯科治療の歴史に大きな貢献を果たした人物です。
このアングル博士が、100年以上前に考案した不正咬合の分類が、アングルの分類です。
アングルの分類では、上顎と下顎の歯並びの前後的な関係性を重視しています。
その上、アングルの分類を評価するときには、特別な計測器具はいりません。
歯型をとって作った石膏模型があれば十分です。
しかも、評価の方法もとても簡単で、矯正歯科治療のベテランでなくてもできる優れた方法です。
そのため、実際の矯正治療の現場でもとても重宝しています。
○アングルの分類の実際
アングルの分類は、上顎と下顎の第一大臼歯、いわゆる6歳臼歯の前後的な位置関係を基準にして、1〜3級に分類して判断します。
1級は、上顎と下顎の第一大臼歯の噛み合わせが正常な歯並びです。
2級は、下顎の第一大臼歯が上顎の第一大臼歯に対して後ろに下がっている噛み合わせです。
上顎前突(出っ歯)がこれにあたります。
ここから2級はさらに1類と2類に分類され、1類は上顎の前歯が前方に傾いている歯並び、2類は上顎の前歯が後ろに傾いている歯並びになります。
3級は、下顎の第一大臼歯が上顎の第一大臼歯前に対して前側で噛み合っていることで、下顎前突や受け口として知られている噛み合わせになります。
○アングルの分類の問題点
とても優れて、100年以上にわたって矯正治療の診断の基礎となっているアングルの分類ですが、問題がないわけではありません。
それは、アングルの分類の基準ともなっている第一大臼歯にあります。
実は、第一大臼歯が本来の位置になければ、この分類法は正しく評価しにくくなるのです。
そのため、第一大臼歯が本来の位置にあるのかをまず評価しなくてはなりません。
特に、第一大臼歯より前に生えているいずれかの歯に大きな虫歯がある場合や、歯がなくなっているような場合は、本来の位置からずれている可能性が高いため、要注意とされます。
左右の第一大臼歯の位置が前後的にずれているときや、必要以上に前に向かって傾いているときもずれが疑われます。
もし、第一大臼歯の位置がおかしいと思われる場合は、上顎と下顎の犬歯や小臼歯(第一大臼歯の前の歯)の位置関係も考慮に入れて判断します。
■顎骨の異常の改善
顎骨の異常には、①上顎骨の形や位置の異常、②下顎骨の形や位置の異常、③上顎骨と下顎骨の垂直的な位置関係の異常の3つがあり、それぞれの改善が治療目標となります。
○上顎骨の形や位置の異常
上顎骨の形の異常の例としては、骨格性の上顎前突症が挙げられます。
これは、上顎の前歯が傾くなどして、下顎の前歯より前に出ているような上顎前突ではなく、上顎骨自体が前方に成長しすぎたことで生じる上顎前突症です。
このような症例では、上顎と下顎の歯並びだけを整えても異常は解決できないので、骨格そのものも治療の対象となります。
○下顎骨の形や位置の異常
下顎骨の形の異常は、骨格性の下顎前突症が代表的です。
下顎骨自体が上顎骨よりも過度に前に向かって大きくなりすぎている不正咬合です。
上顎骨のそれと同じく、歯並びだけをよくしようとしても問題は解決しないので、骨格自体の治療も必要です。
○上顎骨と下顎骨の垂直的な位置関係の異常
上顎骨や下顎骨の骨格異常というと、先にご紹介した前方へ位置異常がイメージしやすいことでしょう。
ところが、顎の骨格は3次元のものですから、上下方向への位置異常もあります。
具体的には、開咬でよくみられる下顎骨の前上方へ過度な成長発育です。
やはり、上顎骨と下顎骨の治療も平行して行う必要があります。
■横顔の異常
横顔は、上唇と下唇の位置関係を基準にして異常があるかどうかを判断します。
具体的には、鼻の先端と下顎の先を結ぶラインを引いて、このラインに対して、上唇と下唇がどのような位置にあるのかを判断します。
なお、このラインをE-ラインとよんでいます。
E -ラインと上唇、下唇の関係性については、時代とともに変化しています。
長期間の矯正治療も治療の目標が決まっているとわかりやすいですよね。
ぜひ三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科へご相談ください。